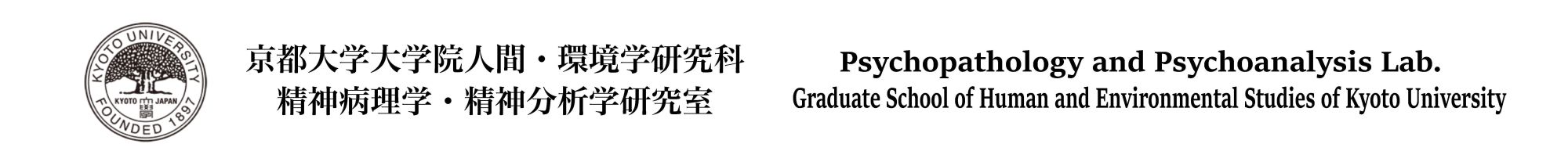「罪ほろぼし」としての精神病理学(追悼・木村敏)
松本卓也
いつの頃からか「戦後」は終わったらしい。植民地支配や侵略、そして「あの戦争」への反省は過去のものとされ、「未来志向」という空虚な言葉がそれに代わるようになって久しい。人口のほとんどが「戦後」生まれとなり、「あの戦争」とは直接的な関係をもたなくなり、「あの戦争」の体験を証言することができる人々も次第に少なくなっているからであろう。中井久夫が指摘するように、「戦争を知る者が引退するか世を去った時に次の戦争が始まる例が少なくない」とすれば、過去の出来事についての反省——木村敏の言葉をつかえば、「罪ほろぼし」の意識——は、どうやら私たちが野蛮にふたたび舞い戻らないための重石として機能していたのであろう。
日本の精神医学において「あの戦争」の位置にあるのは、おそらく60年代末からの反精神医学(あるいは、それと一部共鳴した精神医療改革運動)であろう。それまで抱えてきた矛盾が一挙に白日の下に晒され、精神医療は国家による精神障害者の排除を合理化するための営みであると批判された。批判の影響は広範囲に及んだ。主要な学会の総会は中止になるか討論集会にあてられ、患者を「研究」するということ自体が問題とされ、学会誌は延々と続く討論の場となった。とりわけ、特定少数の患者の主観的体験の把握に注力するタイプの精神病理学は、いわゆる「100分の1批判」に耐えられるはずもなかった。1964年に設立された日本精神病理・精神療法学会は、学会紛争のあおりをうけて1969年に解体を余儀なくされた。
こうして、1970年代以降の精神病理学者たちには、運動によって焦土となった場所を、戦火が収まった後にどのように立て直すか、という課題が否応なく課されることになった。笠原嘉(1928年生)、中井久夫(1934年生)、そして木村敏(1931年-2021年)といった「精神病理学第二世代」を代表する人物がみな、反精神医学を語るときにかならず名前があがるR・D・レインに敬意を払うことを忘れていないことはその証拠のひとつである。実際、笠原はレインの著作を数多く翻訳し、中井は追悼文を書き、それを補足して『レイン わが半生——精神医学への道』の解説として寄稿した。
もちろん、だからと言って、この世代の精神病理学者たちが反精神医学的であったというわけではない。むしろ彼らは、精神医療をどのように「軟着陸」させるか——つまり、精神医学にノーをつきつけた反精神医学のインパクトを否認するのではなく、受け止めた上で、それでも精神医学に対して絞り出すような声でイエスと言い、どうにかして精神医療を、そして精神病理学を成立させうる土壌を再整備する——という困難な課題に取り組んだのであった。学会活動が不可能になるのと入れ替わるようにして1972年から開始された『分裂病の精神病理』ワークショップが、本邦が世界に誇ることのできる精神病理学的思考の絶頂の記録であることは疑いないが、その理由のひとつは、あの時代が要請した緊張感によって襟を正すことを参加者たちが余儀なくされたからではなかっただろうか。
木村敏が『分裂病の精神病理』ワークショップの初回に発表した論文は、「あらためて述べるまでもなく、「精神分裂病」の概念は今日根本的な検討を迫られている」という書き出しで始まっている。ここには反精神医学や精神医療改革運動への直接の言及はないが、聴衆の誰しもがその背景を即座に理解したことは疑い得ない。そして、この論文において木村が主張した、「自己」とは決して固定した所有物ではなく、安定した堅固な土台でもなく、そのつど刻一刻と不断に獲得しつづけていくべき「自己になるということ」である、というテーゼもまた、木村自身にとって「(反精神医学の後に)精神病理学とは何であるか」を根底的に問い直す再整備作業の礎石として据えられたものであるように思われる。そのことは、当該の論文が収められている『分裂病の現象学』の序論にみられる次のパッセージを読めば明らかであろう。
ブランケンブルクのゼミで、私はレインという人が一風変わった分裂病論を書いていることを初めて知った。ブランケンブルク自身は、現象学は成因論に関知せずという立場を固持していたため、レインに対してはかなり距離を置いていたが、私は一時期、レインに対して非常な親近感を抱いた。(…)日本の精神神経学会の騒ぎが始まる前にドイツに渡ってしまっていた私も、いやおうなく反精神医学思想についての自分自身の姿勢を考えざるをえなくなっていた。元来、私は伝統的精神医学に対してはかなり極端な否定論者であり、この態度は『自覚の精神病理』でもはっきり述べられている。分裂病が「病気」ではなくて、他人との関係において歪められた「生き方」だという考えは、私自身の内部ではとっくに自明のことになっていた。このような特別の生き方の源泉にたちもどってその成立過程を考えてみようという成因論的な問題意識が、私とブランケンブルクとの唯一の大きな違いである。
木村の仕事の出発点は、ビンスワンガーやブランケンブルクといったドイツ語圏の精神病理学を輸入し、京都学派の伝統とそれらを結びつけたところにあると説明されることがあるが、実際にはレインの反精神医学への応答という側面をもっていた。少なくとも、それがブランケンブルクのような「本場」の精神病理学との違いであったようだ。その意味で、木村や、彼と同世代の幾人かの精神病理学者の立場は、ふつうの意味での「反・反精神医学」ではありえなかった。繰り返すが、それは反精神医学のインパクトを受け止めた上で、それでも精神病理学を軟着陸させようとするものだったのである。
反精神医学を肯定するのでなければ、ふつうの意味での「反・反精神医学」になるのでもない、というこの困難なひねりには、いくつかのやり方があった。それがユーモアとして展開されていれば、下の世代の向谷地生良が言うところの「半精神医学」(医学的権力と闘うよりも、むしろ当事者同士の横のつながりを重視し、そこからそれぞれの当事者の特異性を析出させるために、既存の医学に対してはそれを「半分借りる」という態度をとる立場)にも接近しえたであろう。中井久夫が1980年に発表した「世に棲む患者」は、統合失調症者を「正常」なマジョリティの棲まう現実へと適応させるのではなく、むしろマイノリティたる統合失調症者がそれぞれの特異的な仕方で現実のなかに棲みうること——言い換えれば、この「世」それ自体が、ひとつの現実であるとともに、マジョリティのように「生活圏を一歩一歩、連続的に同心円的に拡大してゆく」ような仕方で獲得されるのではない「思いがけない」別の現実でもありうること——を示すものであった。言うまでもなく、この議論もまた、レインの「分裂病旅路説」を正面から受け止め、マジョリティの帝国主義に対して逃走線を引こうとするものであった。
反精神医学に対する木村の応答は、中井のような軽やかな斜めへの逃走を可能にするものではなく、自己、そして生命という深淵に向かって、慎み深く錘を垂らしていくものであった。そのことは、1973年に刊行された『異常の構造』にみることができる。そこでは、いわゆる「正常者」が「1=1」という根源的な公式から、統合失調症は「1=1」に「1=0」という「非合理的」とされる公式を加えた二重構造から把握され、「1=0」を理解しえない前者が後者を「差別」していることが論じられる。さらに木村は、非ユークリッド幾何学の例を用いながら、「1=0」の公式が正当でもありうる可能性を示唆しつつ、しかしそれが生命を否定する公式であること、そして合理性を前提としなければ非合理も存在しなくなるような非対称的な関係が合理と非合理のあいだにはあることから、自分が「しょせん「正常人」でしかありえ」ず、それゆえ統合失調症者に対して「罪ほろぼし」の意識をもたざるをえないことを次のように告白する。
反精神医学がその特徴としている常識解体をどこまでも首尾一貫して押し進めれば、それは必然的に社会的存在としての人聞の解体というところまで到達せざるをえず、したがってまた、個人的生存への意志という、生物体に固有の欲求の否定に到達せざるをえないはずだからである。反精神医学は、自己自身を徹底的に追求すれば、窮極的には反生命の立場に落ち着くよりほかはない。したがって本書は、最初意図された反精神医学的な構想とはうらはらに、いわば反・反精神医学的な色彩をも帯びることになった。(…)私たちが生を生として肯定する立場を捨てることができない以上、私たちは分裂病という事態を「異常」で悲しむべきこととみなす「正常人」の立場をも捨てられないのではないか。/私は本書を、私が精神科医となって以来の十七年余の間に私と親しくつきあってくれた多数の分裂病患者たちへの、私の友情のしるしとして書いた。そこには、私がしょせん「正常人」でしかありえなかったことに対する罪ほろぼしの意味も含まれている。
「未来志向」の世代にとって次第にかつての重石が機能しなくなるであろうことと同じように、おそらく、木村敏の存在を感じることができなくなった世代の精神科医にとって、「しょせん「正常人」でしかありえ」ないという彼の諦念と、それゆえの「罪ほろぼし」の意識は機能しなくなってしまうのかもしれない。そして、ここで木村が書いている「反・反精神医学」という言葉は、苛烈な自己否定の時代のあとに彼と同世代の幾人かの精神病理学者たちがひねりを加えた意味ではなく、ふつうの意味での「反・反精神医学」として読まれてしまうようになるのかもしれない。中井もまた、同時代の良心的精神科医たちに対して「うしろめたく思いながらでは良くなる患者もよくならん」という言葉を残したが、それとて「うしろめたさ」を前提とした逃走線の上でつぶやかれた言葉であったことも忘れられてしまうのかもしれない(おそらくは、すでにそうなりつつある)。
「治療」、「適応」、「正常/異常」……といったものは、問い返す必要のない自明の前提となってしまうのかもしれない。それは、臨床において物事を根本的に問い直す精神病理学という営みの(何度目かの、しかし根本的な)死を意味することになろう。残された者にできることは何か? その歴史を語り継ぎながら、根本的に考えることをやめないこと——それこそが、木村敏に対する恩義を忘れないことであるような気がしている。
(まつもと たくや・精神病理学)
*初出:現代思想 49(12) 195-198 2021年9月